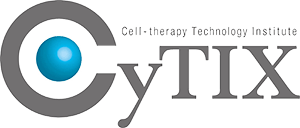インスリン抵抗性の状態が生活習慣病の1番の根本原因だという今まで語られてこなかった研究結果
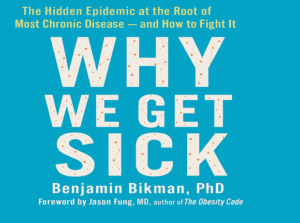
1. インスリン抵抗性を管理することが予防医療の第1歩
ベンジャミン・ビクマン教授(Benjamin Bikman, PhD, Brigham Young University 教授)の「WHY WE GET SICK – The Hidden Epidemic at the Root of Most Chronic Disease – and How to Fight It 」は、インスリン抵抗性の重要性について分かりやすく書かれた現代予防医学の名著だと思います。
この本の中でビクマン教授は、数々の研究報告を俯瞰的に見た上で「インスリン抵抗性こそが、老化性慢性疾患の根本原因であり、その改善方法はこうである」という明確な道筋を示しています。
そこで、ここではそのパート1である「インスリン抵抗性とは何で、老化性慢性疾患との関係は何か」の抄訳をご紹介します。
2. インスリン抵抗性 (Insulin Resistance) とは何ですか?
アメリカ人成人の半数、そしておよそ3人に1人のアメリカ人がインスリン抵抗性の状態です。この数字は88%にまで上昇します。
インスリン抵抗性を持つ人間の80%が先進国に住んでおり、アメリカ同様に、中国やインドの成人の半数がインスリン抵抗性を持っています。
International Diabetes Federationによると、過去30年で倍増し、今後の20年で更に倍増すると予測されているのです。
元々は、富裕層の病気、裕福な高齢者の状態だったのですが、最近では全く様相が一変し、北米の子供の10%がこの状態ですし、後進国のインスリン抵抗性人口が先進国のそれを超えています。
そして何よりも、インスリン抵抗性の状態にある人は、そのことに気付いていませんし、そもそもインスリン抵抗性が何であるかも知らないのです。
インスリンとは
多くの人は、インスリンを糖尿病の薬だと思っています。しかし、インスリンは実際には、我々の体の中で作られているホルモンです。他のホルモンと同様に、インスリンは特定の臓器で作られるタンパク質で、血液によって体の他の部分に影響を与えるものです。インスリンの場合のその臓器とは、膵臓です。
我々が食べ物を口にすると血液中の血糖(グルコース)が増加しますが、そうすると膵臓はインスリンを分泌します。インスリンは、血糖(グルコース)を他の臓器、例えば脳、心臓、筋肉や脂肪組織に取り込むように誘導します。
しかし、インスリンの働きは、この血糖(グルコース)を制御することに留まらず、実は体の全ての組織の全ての細胞に影響を及ぼしているのです。ホルモンの中でも、これほど多くの細胞に影響するホルモンは他にありません。
インスリンの作用は、細胞によって異なります。例えば、インスリンが肝細胞とつながると、肝細胞は脂肪を作りますし、インスリンが筋細胞とつながると、筋細胞は新たなタンパク質を作るといった具合です。頭のてっぺんから足の先まで、インスリンは細胞に、エネルギーの使い方を指示し、細胞の大きさを変化させるよう指示し、ほかのホルモンの生産に影響を与え、遂には細胞の生死までも決める働きを持っているのです。インスリンの一連の作用は同化作用と呼ばれます。インスリンは同化ホルモンなのです。
インスリンは、その働きから、非常に重要です。その重要なホルモンが正常に作用できなくなった状態こそが、インスリン抵抗性(Insulin Resistance)の状態なのです。
インスリン抵抗性を定義する
端的にいうと、インスリン抵抗性とは、インスリンホルモンに対する反応低下のことです。細胞がインスリンに反応しなくなると、インスリン抵抗性になったといい、最終的に体中の細胞がインスリン抵抗性になった時に、体がインスリン抵抗性になったといいます。
この状態では、細胞は同じ反応をするためには普通の状態より多くのインスリンを必要とします。したがって、この状態では普通の状態よりも血中インスリン濃度は高くなりますが、そのインスリンが体により効かない状態になっているのです。
前述したように、インスリンの重要な働きとして血糖(グルコース)の制御があります。血中の血糖(グルコース)値が高い状態が続くことは危険で、時には致命的ですので、体は血液から血糖(グルコース)を移動させて、通常の血糖(グルコース)値に戻そうとします。
しかし、インスリン抵抗性になると、このプロセスが機能せず、血中の血糖(グルコース)値が高い状態、世界共通の糖尿病の兆候である高血糖症(Hyperglycemia)になるのです。ただしインスリン抵抗性は、2型糖尿病になるはるか以前から発生しているのです。
インスリンは血糖(グルコース)と共に語られることが多いのですが、インスリンの果たす役割からすると、注目度が不当に低い気がします。糖尿病を語る時も、血糖(グルコース)ばかりが注目されて、インスリンは二の次です。
血糖(グルコース)は、糖尿病を診断したりモニターしたりする場合に最も使われる血液指標ですが、実は脇役であって、本当は我々は、真っ先にインスリン値を注目しなければならないのです。では、どうして主役が入れ替わってしまったのでしょうか。
何故、血糖(グルコース)ばかりが注目され、インスリンは注目されないのか
科学的には、血糖(グルコース)はインスリンよりずっと簡単に測定できるのです。血糖(グルコース)の測定は、簡単な酵素付の棒または簡単な血糖値計があればよく、この技術はかれこれ100年前からありました。
ところが、インスリンはその分子構造から測定が難しく、放射性物質を用いたその測定法は1950年代後半にやっと知られるようになったのです。現在は、インスリンの測定は少しはましになっていますが、それでもあまり簡単ではなく、すごく安価な訳でもないのです。
ということで、インスリン測定が普及する前に、糖尿病は血糖(グルコース)の病気であるということになっており、血糖(グルコース)値が糖尿病を決め手であるこということが常識になってしまったということです。
それにしても、インスリン抵抗性を糖尿病の指標としてもいいと思うのですが、世の中は一向にその方向に動きません。
何故かというと、インスリン抵抗性が必ずしも高血糖症(Hyperglycemia)の状態ではないからなのです。つまり、インスリン濃度は高いけれど、それでもインスリンが働いているので血糖(グルコース)値は正常という状態が存在するのです。
インスリン値は、毎年毎年徐々に、時には十年単位で上昇していきます。しかし、血糖(グルコース)値ばかり気にしていますから、インスリン値の上昇は誰も気に留めず、最後の最後で糖尿病と診断されてしまうのです。
インスリンはおそらく血糖(グルコース)値よりも、優れた2型糖尿病の病態指標であるはずです。インスリンは血糖(グルコース)値が上がる20年前から、その状態が悪化していることを知ることができるのです。
つまり、2型糖尿病はインスリン抵抗性が進んで血糖(グルコース)値を血中濃度が医学的に妥当だと思われる限界の126mg/dL以内に抑えられなくなった状態であると言うことができるのです。
この考え方は新しいものではなく、1931年にドイツのWilhelm Faltaが提案しています。
また、インスリン抵抗性は高血糖症(Hyperglycemia)の状態です。つまり、インスリン抵抗性を持っている人は、通常より血中のインスリン濃度は高いということです。
あえて申し上げると、インスリン抵抗性だけでは人は死に至りません。しかしながら、他の病気を誘引して致命的な状態に陥らせるものです。ということは、人々が経験するいくつもの広範な健康上問題は、実はこのひとつの根本原因を気を付ければ改善するということなのです。
確かに、インスリン抵抗性は、数多くの深刻な慢性疾患を呼び起こします。例えば、脳、心臓、血管細胞、生殖器官などなどです。放っておくと深刻な状態を引き起こします。インスリン抵抗性を持った人のほとんどが、心臓疾患や他の循環器系疾病で亡くなり、あるいはアルツハイマー病を発症したり、乳癌や前立腺癌になったり、死に至るような数多くの病気になったりしています。
インスリン抵抗性が、このように数多くの疾患の原因であることを理解すれば、インスリン抵抗性が無視できない状態だということがご理解いただけるでしょうか。
3. 心疾患
心疾患は、世界的にも病気による死因の30%以上を占めています。それほど重要なので、心疾患の犯人については、喫煙や飲酒、食事からとるコレステロール、運動不足、多すぎるおなかの脂肪など様々な説が言われて来ました。
しかし、インスリン抵抗性については焦点が当たってきませんでした。実は、インスリン抵抗性と循環器疾患はほとんど分けようがないくらい密接な関係があります。インスリン抵抗性の解明に一生をかけた著名な研究臨床医のJoseph Kraftは、「循環器疾患でありながら、糖尿病(あるいはインスリン抵抗性)の合併症が無い事例というのは、単に診断していないだけである。」と言っています。
実際、心疾患という言葉は、包括的な言葉で、心臓や血液細胞にまつわる様々な状態を指し示すものです。心疾患の意味するものとしては、高血圧、心臓筋肉の肥大、血管プラークなど様々です。
高血圧
過剰な高血圧は、心疾患発病のリスクを非常に高めます。血管の圧力が増すと、心臓は体全体の全ての組織に血液が行きわたるようにより一層働くことになります。心臓はこの状態をそれほど長く続けられないので、治療しなければ、状態は悪くなります。
インスリン抵抗性と高血圧の関連性については、議論を待ちません。高血圧の人は、必ずインスリン抵抗性があります。しかし、最近になって分かってきたのは、インスリン抵抗性がありインスリン濃度が高いということが直接的に高血圧を起こしているというkとです。
問題はインスリン抵抗性がある人が、ほとんどそのことを認識していないということです。高血圧だと診断されたならば、それはインスリン抵抗性であるという最初の証拠なのです。反対に、インスリン抵抗性が改善すれば、高血圧も直ぐに改善するのです。
塩分と水分の貯蔵
インスリンが血圧を高める方法のひとつは、アルドステロン(aldosterone)ホルモンに対する反応としてです。アルドステロンは心臓に対する重要な役割を持っています。腎臓の上に位置し、体内の塩分と水分のバランスを調整している副腎からアルドステロンは分泌されます。
塩分を構成するナトリウム(sodium)と塩化物(chloride)は、共に重要な電解物(electolytes)で、体中の細胞が正常に機能するようにしています。アルドステロンは、腎臓にナトリウムを保持したり血中に再吸収させたりするように指示し、尿から排出しないようにしています。
従って、もし副腎がより多くのアルドステロンを血中に分泌させると、あなたの体はより多くのナトリウムを保持しようとしますので、ナトリウムと共にある水分も保持しようとするのです。これが血中の水分量を増やす結果となり、血圧が上がる要因になるのです。
インスリンは、体内のアルドステロンを増やします。従って、インスリン抵抗性で血中のインスリンが高ければ、アルドステロンも以上に増えることになり、血液量が増えて結果的に血圧を上げることにつながるのです。
厚くなった血管
高いインスリン濃度が高血圧を引き起こすもうひとつの方法が、厚くなった血管壁にあります。血管は何層にも重なった構造になっていますが、最も内側の層は、内皮細胞(endothelial cells)或は血管内皮(endothelium)と呼ばれる細胞で出来ています。
インスリンは同化ホルモンであったことを思い出してください。インスリンは、いつであっても細胞に成長シグナルを送りますので、内皮細胞に対しても同じです。これは極自然な反応です。
しかし、過剰なインスリンが血中にある場合、このシグナルは強まります。血管壁の細胞が成長すれば、血管内は狭くなります。こうして血圧が高くなるのです。
血管が広げられない
窒素(NO)は強力な血管拡張作用を持っていて、内皮細胞は窒素を生産します。窒素は、血管筋をリラックスさせるので血管が広がるのです。
インスリンは、内皮細胞中の窒素生産を促進します。インスリンが血管を通過すると、内皮細胞に窒素を生産するように指示しますので、血管は拡張し、その部分の血流が良くなります。ですから、筋肉が栄養や酸素を必要とする時には、インスリンが血流を良くして助けているのです。
一方、先の循環器の問題でお話したように、インスリン抵抗性によってアルドステロンと内皮細胞が過剰反応していますので、窒素とインスリン抵抗性の問題とは内皮細胞が十分な窒素を作れなくなるということなのです。この場合、内皮細胞がインスリンの窒素生産指示に対して上手く反応できなくなるということを指しています。
狭い血管
交感神経は、心臓の鼓動や心臓収縮力や血管サイズや発汗等の体の無意識活動を制御しています。この働きの中に血圧を上げるということがあります。一般的には高い血圧は悪いことに思われていますが、戦ったり命を守るために逃げたりするためには、血圧が高いことによって血液が体全体に行きわたりますので、特に筋肉に栄養や酸素を多く供給するので非常にいいことです。
興味深いことに、特段の危機がなくても、インスリンは前記のスイッチを入れる傾向があります。インスリンが過剰にある状態が続く限り、血圧が上がった状態になるのです。
血液脂質の不健康化
脂質は、脂肪や脂肪のような物質で、血液や組織内にも存在します。体は脂質を将来のエネルギー源として備蓄し、エネルギーが必要な時には、脂質を脂肪酸に分解してグルコースのように燃焼させて使います。脂質異常(Dyslipidemia)とは、血液中に異常な量の脂質が存在する状態のことです。
脂質には主に、中性脂肪(triglycerides, TG)、低密度リポタンパク質コレステロール(LDL)、高密度リポタンパク質コレステロール(HDL)の3種類があります。
医師の中で、長く信じられてきた通説として、HDLは良いコレステロールで、LDLコレステロールは悪者という考え方があります。確かにこれを裏付けるデータもあるのですが、より多くの研究がこれとは逆の結果を示しています。
この混乱は、その測定方法にあったのです。測定には大きさと密度が使われます。大きくて密度の小さいパターンAと、小さくて密度の高いパターンBに分けて考えると、コレステロールが病気の原因となるためには血管壁を通過しなければなりませんから、大きさが小さい方がその役割に合っているということになります。
ですからパターンBのLDLコレステロールを持っている人の方が、パターンAを持っている人よりも心疾患になりやすいのです。
しかし、今現在では、LDLの大きさを計る検査は一般的ではありません。しかし、TG、HDL、LDLの数値があれば、予想がつきます。TG(mg/dL)をHKL(mg/dL)で割ると、驚くほど正確にLDLの大きさを知ることができる指標になるのです。
数値が低いほど(例えば2.0以下)、LDLサイズは大きくパターンAに近いということです。数値が高いければ(2.0以上)、LDLサイズは小さくパターンBに近いということになります。このことを覚えていれば、LDLサイズは予測ができるのです。
インスリン抵抗性との関係はといいますと、インスリンはLDLパターンBを肝臓で選択的に生産するように促進します。インスリン抵抗性でインスリン濃度が常に高い状態になると、肝臓はLDLパターンBが多くなる傾向になるのです。
脂質異常と高血圧との関係を端的に言い表すと、血管壁に脂質が集積し、粥型アテローム硬化型のプラークが生成され、血管の内径が狭くなるということです。(実際はもう少し複雑なので、後術します)
アテローム性動脈硬化(Atherosclerosis)
これは、心疾患が進む最も典型的なプロセスです。これを詳しくみてきましょう。コレステロールは血管壁を通過する必要があります。しかし、内皮細胞に貯蔵されたコレステロール自身が病気を起こす訳ではありません。内皮細胞内のコレステロールも脂質も良性です。しかし、脂質が良性でいられるのは長くはありません。
コレステロールと脂質が悪性化するのは、酸化するからです。酸化ストレスが高いとそうなります。酸化が起こると、マクロファージという白血球が酸化した脂質を貪食し、他の細胞が酸化しないようにします。
しかし、やがてマクロファージは酸化した脂質とコレステロールで手が回らなくなり、脂質が占領した細胞、いわゆる泡沫細胞(foam cell)になってしまいます。この泡沫細胞は、より多くのマクロファージが近くに来るようにシグナルを出します(この状態を、炎症反応と言います)。
新たに来たマクロファージも時間を経て泡沫細胞になりますから、状態は悪化するばかりです。こうして、泡沫細胞と脂質が重なり合い、アテローム型プラークの元が出来て来るという訳です。
コレステロールばかりが悪者扱いされていますが、コレステロール以外の脂質にも悪者がいます。特に、多価不飽和脂質(polyunsaturated fat)であるリノリウム酸(linoleic acid, 大豆油などの種子油に多い)は、コレステロールよりもはるかに早く急速に酸化しやすい脂質なので、重要な犯人のひとつであると言えます。
実際には、コレステロールが酸化される際には、リノリウム酸がコレステロールにくっついて酸化リノリウム酸になっていることが多いのです。
インスリン抵抗性は、アテローム性動脈硬化の重要なリスク要素です。その理由のひとつは前述したように、インスリンはLDLパターンBのコレステロールを増やし、このLDLパターンBのコレステロールは、リノリウム酸などの問題ある脂質を運ぶからです。
もうひとつの理由は、酸化ストレスにあります。インスリン抵抗性は酸化ストレスを増幅するのです。そして後ほど、酸化ストレスがインスリン抵抗性を増やすという双方向性についても見ていきます。
炎症
炎症の指標として、特に有名なC反応性タンパク質(CRP)は、コレステロール値よりも正確に循環器疾病を判別します。特筆すべきは、インスリンは、インスリン感受性が高い人に対しては抗炎症反応を高めるのですが、インスリン抵抗性の人に対しては炎症を促進するのです。
これは問題です。インスリン抵抗性は、先ず高血圧により、血管損傷を引き起こす可能性を高めます。次に、インスリン抵抗性は、血管壁への脂質の堆積を促進します。
最後に、インスリン抵抗性は、マクロファージによる血管壁の炎症を促進し、マクロファージが酸化脂質に乗っ取られて泡沫細胞化し、炎症を高めるのです。これらすべての現象が、最終的にはアテローム型プラークの生成を生むのです。
心筋症(Cardiomyopathy)
循環器疾病の中で、心筋に関するものがあります。心筋症とは、心臓の筋肉が血流を十分送り出す力を出せなくなる状態です。心筋症には3つのタイプがあると言われています。
拡張性心筋症(dilated cardiomyopathy)
肥大性心筋症(hypertrophic cardiomyopathy)
限定的心筋症(restrictive cardiomyopathy)
いずれの心筋症も、非虚血性心疾患(nonischemic heart failure)と呼ばれます。血流不足が原因ではないという意味です。
これら3つの中で、インスリン抵抗性が最も関係しているのは、拡張性心筋症(DCM)です。心筋細胞は、エネルギー源としてもっぱらグルコースに頼っています。
DCMでは、心筋が拡張、すなわち引き延ばされて薄くなっています。この状態では、心筋は普通に収縮するのが難しくなり血液を上手に送り出すことが出来ません。心筋はよりグルコースを必要とする状況になっていきます。
しかし、インスリン抵抗性は、心臓がグルコースを取り込んで使う力を減少させます。インスリン抵抗性とDCMの関係性は余り研究が多くないのですが、肥大性心筋症の関係性を示す研究は複数存在します。
もうお気づきかと思いますが、インスリン抵抗性ほど心疾患の原因としてふさわしい状態は他にありません。心疾患リスクを下げたいのであれば、インスリン抵抗性をなんとかしなければなりません。
心疾患を防ぎたいという努力は長くなされてきていますが、インスリン抵抗性の重要性は無視されてきたというのが本当のところなのです。
4. 脳と神経の疾患
20年前までは、脳はインスリンに対して無反応の臓器であると規定していました。現在では全く様変わりで、インスリンは脳の沢山のプロセスを制御していることが研究により明らかになっています。
体のすべての細胞と同様に、脳細胞にもインスリン受容体が存在し、正常に機能するようにインスリンを察知し反応しています。インスリンは脳に燃料としてグルコースを取入れるように促し、脳細胞が成長し生存するように助けています。
またこのホルモンは、食欲を制御し、エネルギーをどう使うかも制御していますので、(食事にあとに起こるように)インスリンが体内に増加したことを脳が察知すると、食欲が減少するのです。
更には、インスリンは学習や記憶形成にも重要な役割があります。脳の機能にとって、インスリンは重要です。ですから、インスリン濃度が高まり、脳がインスリンに反応しにくくなる、即ち脳がインスリン抵抗性の状態になると問題が生じます。
最近の研究では、インスリン抵抗性の状態が10年続くごとに、脳は多く2年老化するというのです。
アルツハイマー病に関する新しい理解
認知症(dementia)とは、主に記憶の喪失と日常生活を送る知的能力の欠如を指しますが、様々な疾患が重ね合わさったものと言えます。代表的なものが、アルツハイマー病です。
認知症の80%近くを占め、世界中では30百万人の患者がいると言われています。このままの状況が続けば、20年毎に患者は倍増していきます。その原因も治療法もまだ余り分かっていない現状がある一方で、インスリン抵抗性とアルツハイマー病の関係性は明らかになってきており、アルツハイマー病を第3の糖尿病という呼称も生まれているのです。
アルツハイマー病は、アミロイドβペプチド(Aβ)で出来たプラークが集積していると考えられています。アミロイドはタンパク質片で体は普通に生産しています。これがプラークという塊となると、脳の普通の機能である記憶、気分、動作機能、学習などが妨げられるのです。
Aβプラークは有害なので、脳はこれが形成されないようにする機能を持っています。代表的なものは、アポリポタンパク質E(APOE)と言います。これが正常に機能している時は、必要なコレステロールを神経に運んだり、Aβプラークを分解したりします。
APOEには3タイプの遺伝子がありますが、15%くらいの人がAPOE4というバージョンのAβプラークを分解できない遺伝子を持っています。APOE4遺伝子を持った人は、70歳代半ばで10倍から30倍の確率でアルスハイマー病を発症します。
ある研究ではAPOE4とアルツハイマー病の相関は高かったのですが、(p=0..0001)この次にアルツハイマー病と相関性が高かったものには、年齢(p=0.005)や学歴(p=0.002)を抑えて、空腹時インスリン値(p=.0005)だったのです。
血管性認知症
アルツハイマー病の次に多い認知症が、血管性認知症です。血流が十分でない場合に発生することからこの名称となっています。ある研究では、インスリン抵抗性があると血管性認知症になるリスクが2倍になるという結果を示しています。
パーキンソン病
パーキンソン病は、脳疾患のひとつで、体の不自由が一番の主訴ですが、動作速度の減少、手足の硬直、手足の震えのみならず、うつ、睡眠障害、めまい、認知機能障害などを引き起こします。
米国では年間6万人がパーキンソン病と診断されていますが、原因も治療法もまだわかっていません。パーキンソン病のほとんどの人が、その過程で認知症になります。脳の中にLewy bodiesと呼ばれるタンパク質が堆積されることが分かっています。
もっと重要なのが、ドーパミン生成神経が失われることです。パーキンソン病とインスリン抵抗性に関係があることが研究により示されています。パーキンソン病の30%が2型糖尿病ということから、おそらくインスリン抵抗性は80%にも及ぶ可能性があります。
偏頭痛
米国成人の18%が偏頭痛に悩まされています。ある研究によると、インスリン抵抗性の人は通常より2倍偏頭痛になりやすいという結果が示されています。
神経障害
2型糖尿病の合併症としての神経障害は広く知られています。インスリン抵抗性が神経障害に関係しているのは明らかです。
5. 生殖機能
次に性とその素晴らしい複雑性についてお話します。性ホルモンは主要な性腺(男性は精巣、女性は卵巣)で脳の作用を伴って作られます。脳と生殖腺は交互に作用して生殖を促しますが、インスリンもここで大きな役割を果たしています。
インスリン抵抗性と不妊が関連していることは、なかなか想像できないかもしれません。インスリンは脳に、生殖に適している状態であるかどうかを知らせています。
げっ歯類の実験では、インスリン不足は生殖腺と脳に作用し、生殖行為を減少させることが分かっています。インスリン抵抗性の男女は、インスリンが効いている男女より、不妊の傾向が強いのです。
インスリンと女性の生殖機能
女性の生殖は複雑です。女性の月経周期に渡って、ホルモン変化が起こり、月1回の排卵までに至ります。妊娠すると、生殖機能は胎児の育成にまで範囲が広がります。出産後も授乳に向けて体は変化します。
女性の生殖には、大掛かりな変化・成長が伴い、多大なエネルギーが必要です。このことから、女性の生殖の方が男性より、インスリンやインスリン抵抗性への関わりが大きくなります。
インスリンは、細胞の大きさや数を増やします。妊娠した体は成長しますので、インスリンがこれを助けています。インスリンは胎盤の成長を助け、母乳の生産を助け、またエネルギーを沢山蓄えられるように脂肪を増やします。
妊娠は、インスリン抵抗性が普通であるめずらしい状態です。妊娠中の女性は、妊娠中はインスリン感受性が半分くらいになります。したがって、この場合インスリン抵抗性はいいことになります。これを「生理学的インスリン抵抗性」と呼びます。インスリンを高くして、胎盤などの組織の成長を促進するのです。
高いインスリン水準は、胎児の成長も助けています。インスリン抵抗性は妊娠では普通ですが、他の女性特有の問題、例えば受精力、多嚢胞性卵巣症候群、妊娠糖尿病、妊娠中毒症など引き起こす可能性があります。
妊娠糖尿病
インスリン抵抗性と関連する生殖関連疾患は、妊娠糖尿病です。これは、インスリン抵抗性が、血中のグルコースを正常値に抑えられない状態を言います。
妊娠前にインスリン抵抗性や2型糖尿病の気がなかった女性でも、妊娠糖尿病にかかった後は、2型糖尿病を発症するリスクが7倍高まります。
妊娠中毒症
妊娠糖尿病で、より深刻なインスリン抵抗性に陥ると、最も生命の危険を伴う妊娠疾患である妊娠中毒症、つまり腎臓機能の悪化を起こす危険性が高まります。妊娠前期にひどいインスリン抵抗性を起こした女性は、妊娠後期に妊娠中毒になる可能性が高くなります。
この二つの疾病の関連性は詳しくは解明されていませんが、インスリン抵抗性による高血圧が、交感神経に働きかけて窒素生成を減少させることに関係あるかもしれません。
インスリン抵抗性による高血圧で、母体の胎盤などに十分な血液が行きわたらない状態になっている可能性はあります。そのような場合、胎盤は、VEGFというシグナルタンパク質を生成します。VEGFは、血管新生を促し、胎盤はより多くの血液を受け取ろうとします。正常な妊娠では、この通りのことが発生しています。つまりより多くの血液を必要とする胎盤をVEGFが助けています。
しかしながら、妊娠中毒症が起こると、胎盤はなぜか溶解性VEGF受容体という二番目のタンパク質を分泌し、VEGFに接着して機能を阻害します。従って、胎盤はVEGFを生産しますが、タンパク質は機能しないのです。
この場合、胎盤を傷つけるだけでなく、腎臓にも深刻なダメージがあります。腎臓は、血液ろ過の過程でVEGFを必要としています。腎臓が十分なVEGFを受け取れないと、機能不全が生じるのです。
正常にろ過機能が働かないと、毒性成分と過剰な水分が血液に入り込み始めます。過剰水分による血液量増加が高血圧の主な原因なのです。しかし、毒性成分はもっと危険で、脳に影響を及ぼし、脳卒中や死をもたらす可能性があるのです。
また、VEGF不足の腎臓は、漏出性の状態となり、血液中のタンパク質を尿に流れ出させるのです。妊娠中毒の場合、血圧のみならず尿中のタンパク質も観察するのは、このためです。
早期の時点で発見し治療しなければ、母体の妊娠中毒症は、肝臓不全や腎臓不全を起こし、将来の心疾患につながります。胎児は、胎盤に十分な血流が行かないと、必要な栄養と酸素が得られないので、出生時体重が低くなります。
妊娠中毒症の唯一の解決法は、安全に出産できるようになった時点で、胎児をできるだけ早く出すことです。自然分娩や早期の帝王切開などで、母体の安全を守ることが必要です。
過体重乳児、未熟児
体重が重すぎたり軽すぎたりする乳児は、後日問題を抱える可能性があり、妊娠中毒症やインスリン抵抗性の母体は、実は非常にこの可能性が高いのです。
母親の代謝状態と乳児のそれとの関係が非常に関連しているということは、第二次戦争後の1994-45のオランダ飢饉研究で明らかにされました。
不十分な母乳
インスリン抵抗性は、母体の母乳生産に影響します。また、授乳は母体のインスリン感受性を増やす自然な方法です。従って、インスリン抵抗性が高いと妊娠によるインスリン感受性を自然な形で元にもどす機会を失わせることになるのです。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
PCOSは、世界で10百万人もの女性の不妊の原因となっています。文字通り、卵巣が嚢胞に覆われ、通常の何倍の大きさに肥大するとても痛い病態です。PCOSはインスリン過剰な状態の病気です。
女性の生殖は、ホルモンが変異すると申し上げましたが、妊娠初期の段階では、エストロゲンの数値は低いです。脳の重要な一部である視床下部は脳下垂体にシグナルを送り、脳下垂体は卵胞刺激ホルモン(FSH)を分泌します。FSHは、卵巣の卵胞に成熟卵となるように指示します。
ひとつの卵が他を凌駕します。卵胞が成熟すると、卵巣からのエストロゲン量が増加し、視床下部と脳下垂体に、卵は排出できるくらい育ったことを伝達します。その時点で、脳下垂体は、黄体ホルモン(LH)を分泌します。LHは、優位の成熟卵を卵巣へと移動させます。これを排卵と言います。このように排卵までは、いくつかのホルモンがそれぞれの役割を果たしているのです。
卵巣はインスリンに反応しています。例えば、インスリンはエストロゲンの生産を阻害します。すべてのエストロゲンは、その生成過程で一度はアンドロゲンになります。アロマターゼという酵素によって、テストステロンのようなアンドロゲン(男性ホルモン)はエストロゲン(女性ホルモン)に変換されます。
しかし、インスリンが過剰な状態だと、アロマターゼを阻害します。酵素の力が落ちると、アンドロゲンは必要な量のエストロゲンになれず、エストロゲンの生産が通常より下がり、アンドロゲンが通常より高くなります。
エストロゲンは数え切れないほどの役割を担っています。女性にとって、重要な一つのさようは、月経周期に於ける役割です。その周期の中間ぐらいで、エストロゲンの生産は非常に高まります。このエストロゲンの増加が脳に指示し、LH生産の量を増やし、それが排卵を促し、他の卵の廃棄を促します。
もし、インスリン抵抗性により、この月経中期におけるエストロゲンの上昇が起こらないと、排卵が起こらず、卵巣は卵を保存し、累積していきます。
エストロゲンの作用以上に、インスリンは脳に直接働きかけてLHの正常な生産を妨害します。LHの生産は波状に起こります。インスリンはこのパターンを阻害し、通常の生殖を阻止します。
インスリンの性ホルモンに対する影響は、生殖阻止に留まりません。PCOSにより、比較的少量のアンドロゲンしかエストロゲンに変換されないので、高アンドロゲンの状態になります。高アンドロゲンは、女性の髭や体毛を濃くし、また男性のような薄毛症をおこします。そして、インスリンだけで、性ホルモンとは関係なく、黒色表皮種といわれるシミを増やす傾向にあります。
生殖治療の問題点
インスリン抵抗性が起こす様々な妊娠異常に対して、抵抗性を持つ女性は、生殖治療を探すようになります。こんな場合でもインスリン抵抗性が影響力を発揮します。
まず言っておきたいのは、減量やインスリン感受性薬など何を用いようとも、インスリン料を減らしてインスリン感受性を高めれば、生殖薬を使わずに、正常な排卵を増やすことができます。
最も一般的な女性の生殖力改善薬が、エストロゲンに作用し排卵を促進するクロミフェンです。しかしながら、PCOSでインスリン抵抗性の女性は、薬の効果は低いので服用量が増え、悪い副作用が増える結果となります。
PCOSの女性には、血中インスリンの測定がクロミフェンの効果を計る一番の指標となります。インスリンが低ければ、反応は高くなります。
女性の生殖がホルモンの複雑なオーケストラだとすると、インスリンは指揮者です。月経周期におけるエストロゲン、FSH、LHなどの性ホルモンの異常な増減は、指揮者に従っているだけです。
もしも女性がインスリン値をコントロールできていれば、性ホルモンもそれに従い、ここで述べたような一般的な不妊症の場合は、性ホルモンが単純に切れてしまっているのです。
インスリンと男性の生殖機能
女性の生殖機能の複雑性に対して、男性の生殖機能は比較的単純です。男性のそれは、精子数の少なさと低い質です。2番目の問題としては、ほとんど見ませんが、解剖学的問題か遺伝子異常です。
ここでは、インスリン抵抗性がもたらす2つの問題である精子の生産と勃起不全に焦点をあてます。テストステロンとの関係から見ていきましょう。
我々は、テストステロンについて文化的な脅迫観念があります。男性が、低テストステロンと診断され、エネルギー不足や体重が減らないことなど他の健康状態のせいにしているのをよく耳にします。多くの人が、低テストステロンは体重増加が原因だと信じる傾向にありますし、現にそれはそうです。
しかし、低テストステロンの診断が増えているのは、何か他の原因が疑われます。男性は、低テストステロンと肥満で不妊の状態を同時に起こしているのだと結論づける前に、その過程を逆からみていくこと、つまり代謝の悪さが実際にはテストステロンの生産低下を引き起こしているのではないかという風に見てみることに価値があるのではないでしょうか。
体脂肪の高い男性は、テストステロンが低い傾向にあり、体重の減少によりテストステロン値は上昇します。もちろん、これらの過程でインスリンは高い関連性を持っているはずですが、その影響は測定しずらいところです。
いくつかの研究では、体脂肪とは無関係に、インスリンは直接的にテストステロンの生産を阻害している、つまりインスリンが多いとテストステロンが低いことが示されています。
精子の生産
精子の生産にも、脳からのホルモンやテストステロンや精巣からのエストロゲンなどいくつかのホルモンが関わっています。これらのホルモンの生産が上手くいかないことが、健康で十分な量の精子を作れなくなる原因となります。テストステロンが通常の水準以下であれば、精子の生産は起こりません。
勃起不全
インスリン抵抗性の男性は、勃起不全になるリスクが高まり、インスリン抵抗性が悪くなれば勃起不全も悪くなります。
その相関性は余りにも高いので、勃起不全はインスリン抵抗性の早期発見指標としてふさわしいと言われている程です。ですから健康そうな若者が勃起不全を患っていた場合、インスリン抵抗性がその原因である可能性は高いということです。
勃起不全は、血管制御の問題が原因であることが多いです。勃起するには、血管が急激に拡張し維持することが必要です。このプロセスには、窒素の生産と反応が必要です。内皮細胞(血管壁の一番内側の細胞)がインスリン抵抗性になると、窒素の生産力が落ち、それが血管の強い拡張シグナルを失わせるのです。
女性の生殖機能がオーケストラだとすると、男性の生殖機能は床屋の四重奏とでもいうところでしょうか。パートは少ないですが、それぞれがかけがえのないものだということです。男性の場合、生殖能力には、肉体的な(勃起のような)ものと、ホルモン的な(精子生産など)ものとが必要ということです。どちらも、インスリンが主要な働きをしているのです。
6. 癌
癌には様々な原因があります。癌は、遺伝子変異と遺伝子損傷の結果であるという説が有力であったが、この説に対する疑問が増えています。癌は遺伝子の病気ではなく、代謝異常だという説です。
癌とは、細胞が無尽蔵に増える細胞増殖の病気です。インスリン抵抗性は、癌細胞が急速に成長するのを助けます。
第一に、癌細胞はグルコースを好物にしています。実は正常な細胞は、勝手に増殖しないような仕組みが備わっており、成長因子といわれる物質の指示がなければ栄養を取り込みません。シグナルがあれば、正常細胞は栄養分を取込み酵素の力を得てそれらを燃焼させ、我々のエネルギーを作ります。
このエネルギー生成は、細胞内のミトコンドリアで行われます。しかし、がん細胞はこの仕組みを変えて別の方法でエネルギーを生成します。およそ100年前にドイツの研究臨床医のOtto Heinrich Warburgが発見したのは、癌細胞はグルコースをほぼ唯一のエネルギー源として使っているということです。
更に、ミトコンドリアでグルコースを分解するのではなく、癌細胞はミトコンドリアの外で酸素を使わずにそれを行っているということです。このウォーバーグ効果という現象は、癌細胞が血液の行きわたっていない場所(すなわち、低酸素の)であっても、急速に増殖できることを説明しています。
第二として、インスリン抵抗性によって、血中のインスリン値は上昇しています。インスリンの作用として細胞に成長せよと指示することであると思っていると、実は困ったことになります。
インスリンの同化作用は、癌細胞の増殖にも同様に作用しますが、特に癌細胞が正常細胞よりもインスリン感受性を高くする場合にはなおさらだということになります。変異によってインスリン感受性が高まった癌細胞は、インスリンのシグナルにより敏感になるのです。
インスリンと癌の関係を更に見ていくと、多くの研究で注目されているインスリン様成長因子1があります。このたんぱく質は、インスリンのように、体の成長を促します。これが、多くの癌で起こっていることです。
グルコースとインスリンのという二つのシグナルの組合せは、高インスリン症の人が、やせ型であろうが太っていようが、およそ倍の比率で癌により死亡するということを導いでいるのです。そして中でも、乳癌、前立腺癌、結腸癌は、インスリン抵抗性とより密接な関連性を持っているのです。
乳癌
インスリン抵抗性と最も関連性が高いのが乳癌です。インスリン抵抗性の高い女性は、乳癌になる可能性が非常に高くなっています。平均的な乳癌では、乳癌細胞には約6倍のインスリン受容体があるという研究があります。ということは、この乳癌細胞は、インスリンに対する感受性が6倍高いということになります。
ですから、研究によると、乳がん患者のインスリン感受性治療が、乳癌の管理には有効だということが分かっています。前に、過剰な脂肪細胞が血中のエストロゲンを増加させるということを申しましたが、乳房の細胞はエストロゲンが送る成長シグナルに敏感です。ですから、例えば肥満などで、これが過剰に起こると、乳房細胞は過剰に成長し、乳癌のリスクが高くなるのです。
前立腺癌
前立腺癌も、インスリン抵抗性との関係性が大きいです。乳房と同じく、前立腺もとてもホルモン感受性の高い組織です。すなわち、ホルモンのシグナルによって成長したり収縮したりします。
テストステロンが主要なホルモンシグナルですが、インスリンも重要な働きをします。良性な前立腺肥大が最初に気になる症状です。これは加齢により生じる症状で、排尿がしにくくなります。
インスリン抵抗性の男性は、普通に比べて前立腺肥大になる可能性が2~3倍高くなります。そして、インスリン抵抗性の場合には、前立腺癌になる可能性は250%高くなると言われています。
また、乳癌と同様に前立腺癌細胞にも過剰なインスリン受容体がみられます。ですから、前立腺癌も、異常な増殖を示すことができるのです。
結腸癌
インスリン抵抗性は、結腸や直腸の癌リスクを高め、結腸癌で死に至るリスクを高めます。結腸癌患者でインスリン抵抗性がある場合は、およそ3倍癌で死亡するリスクが高いのです。インスリンは、腸の一番外側の細胞が増えるように促しているのです。
以上のように、インスリン抵抗性は唯一の原因ではないものの、いくつかの癌腫には非常に関連性が高いことが分かっていますので、環境や食べ物を変えるなど、事前に手を打つことは有意義ではないでしょうか。
7. 老化、皮膚、筋肉、骨
中年になると、自分の衰えに気付くときがあるものです。肌が緩んで乾燥し、筋肉は弱くなり、骨も密度が減りもろくなってきます。老化については、様々な理論が発表されてきましたが、最近では、インスリン抵抗性が老化の原因であるという研究が出てきています。
インスリン抵抗性と皮膚
皮膚は、様々な細胞で構成されていますが、同時に非常にインスリン反応性が高いことも知られています。糖尿病が皮膚の問題をもたらすということはよく言われていますが、以上に乾燥肌だとか、かゆみがひどいとか、皮膚感染症を繰り返すとか、傷が治りにくいなど様々です。
黒色表皮種(acanthosis nigricans)
黒色表皮種は、インスリン抵抗性の初めのサインであったりします。メラニン形成細胞の過剰反応が関連しています。
メラニン形成細胞はインスリン反応性が高いです。血中インスリン値が高ければ、メラニン形成細胞が過活動になり、メラニン生成が過剰となって通常より黒くなるのです。更にこれは、皮膚がよりこすれやすい首、脇の下、鼠径部などに多く発生しやすいですが、大きな範囲で胴体、腕、足や顔に発生したりもします。
肥満や2型糖尿病の人を含めて、インスリン抵抗性の人は黒色表皮種が多くなります。そして、何歳からでも、子供でも、これは発生します。
皮膚のイボ
インスリン抵抗性の人に多く、この皮膚のイボが、首、脇の下、鼠径部に見られます。これは、インスリン抵抗性により、皮膚の形成を助ける角化細胞がより成長し分化することの結果であると考えられます。
乾癬(Psoriasis)
乾癬は、慢性炎症性の皮膚疾患ですが、最も知られているのは、尋常性乾癬といって白や銀色の傷に囲まれた赤みを帯びた部分のことです。乾癬は、肘や膝、頭皮や体の中央部分にできます。何歳でもできますが、子供から35歳の間に出ることが多いです。
免疫や遺伝子が関係していると言われていますが、確かな原因は分かっていません。しかし、インスリンとの関係性が言われていまして、乾癬がある人はインスリン抵抗性などの代謝異常になりやすいです。乾癬がある人は、普通の人より3倍インスリン抵抗性になりやすいことが分かっています。
インスリンと筋肉機能
平均的な中年のひとでは、筋肉量は体重の約25-30%に相当し、体の中で最も大きいインスリン感受性の高い組織ということになります。インスリン抵抗性にとっても、筋肉は重要です。
それは、インスリンに反応して、どれだけの量のグルコースを取り込めるかが非常に重要で、血中のグルコース量が減れば、インスリンは標準値に戻るのです。つまり、筋肉量が増えれば、グルコースを取り込める量も増え、インスリンを低く保つことができるということにもなります。
インスリン抵抗性の場合は、インスリン感受性はほとんど半分になります。筋肉は、体内で最も早くインスリン抵抗性になる組織と言えます。インスリン抵抗性は、筋肉量を減らし、グルコースを取り込む許容量が減り、機能が下がるのです。
筋肉量の低下
サイコぺニアとは、加齢に伴って筋肉が減ることを指す用語ですが、中年以降は、だいたい1年間に1%の割合で筋肉が減っていきます。これはごく普通の加齢による現象ですが、これは、成長ホルモンやアンドロゲンなどのホルモンの変化に起因しています。
しかし、インスリン抵抗性になるということは、インスリンの作用が効かなくなるということで、インスリンの同化作用もそれに含まれますので、筋肉は有力な成長サインを失うことになっています。
筋肉が育つためには、失ったタンパク質を補うためにも十分な細胞タンパク質を生成しなければなりません。これは、タンパク質回転率と言われ、(筋肉の減少が増加に勝る場合)マイナスにもなりますし、(筋肉の減少が増加と均衡)中立にもなりますし、(筋肉が減少以上に増加する)プラスにもなります。
インスリンは、筋肉の増加を促し、現象を抑制する働きがあります。したがって、インスリン抵抗性になれば、筋肉は減っていきます。
繊維筋痛症(Fibromyalgia)
繊維筋痛症は、最も一般的な痛みの病気です。全身の筋肉の痛みは、時にはだるさ、記憶力低下、そして気分の問題と共に発生します。何よりも、痛みの原因を説明できないことが多く、手術や感染、体の感じるトラウマがきっかけとなる場合や、特にきっかけがなく始まる場合もあります。最近の研究で、これらがインスリン抵抗性のために起こっているのではないかという説が出てきたのです。
インスリンは筋肉を健康で強い状態を保ちますし、インスリン抵抗性は筋肉を壊します。筋肉はしっかりとした構造によって動きを作らなければ、まったく意味がないと言えます。その構造とは、骨と関節によって構成されるものです。
インスリンと骨と関節
骨は、骨格を作るだけでなく、立ったり動いたりできるようにしています。また、内臓を守り、ミネラルを蓄え、赤血球や白血球を作ります。また骨は他の組織と同様に常に変化しています。筋肉同様に、健康な骨のマトリックスは入替えが必要です。骨は常にその内容物を破壊しと生産しており、カルシウムや他のミネラルが出入りしています。
これには、2種類の細胞が関与しています。新しい骨を作り強くして古い骨と置き換える骨芽細胞(Ostcoblasts)と、骨を破壊する破骨細胞(Osteoclasts)です。この2種の細胞が、健康な骨の構造を保っています。
骨のインスリンシグナルは、筋肉ほど注目されていません。その結果、骨のインスリン抵抗性もあまり知られていません。しかし、インスリンは骨の健康を守っていることが知られてきました。
インスリンは、骨を育てる骨芽細胞の働きを促進する一方で、骨を破壊する破骨細胞の働きを阻害しているのです。
骨の減少
骨が細くもろくなる骨粗しょう症(Osteoporosis)は有名です。骨粗しょう症になる前の状態として、骨減少症(Osteopenia)も経験します。
骨の健康に対するインスリン抵抗性について研究するには、体重の問題に取り組まなければなりません。脂肪によるか筋肉によるかを問わず、大きな体には大きな骨がありますが、インスリン抵抗性は、より脂肪と関係しています。
インスリン抵抗性の高い人は、重い体重を運ぶ結果として大き目の骨を持っていることが多いのですが、骨の強さは反対に弱い傾向があることが分かっています。この原因については、研究者の見解は分かれます。おそらく、インスリン抵抗性の人が摂取している薬の違いによるかもしれません。
骨の他の働きとして、例えば白血病や血液がんの患者は、骨髄移植を必要としますが、インスリン抵抗性の高い人ほど、骨の総量は減る傾向があることが分かっています。
骨関節炎(Osteoarthritis)
骨は、健康な関節がないと役目が果たせません。骨関節炎、または関節軟骨(joint cartilage)の喪失は、以前は摩耗と引き裂きの病気であると思われてきました。肥満と併発することが多いので、臨床医は重い体を運んだ結果として起きたのだと考えていました。
しかし、最近では、これは代謝異常だという考え方が広がってきました。他の組織と同様に、関節もインスリンを含む代謝シグナルに反応します。多くの研究から、骨関節炎の患者のインスリン値は高いことが分かっています。
関節の重要な部分として、関節軟骨があります。関節軟骨を構成する主要な細胞が、軟骨細胞(chondrocytes)です。もちろん軟骨細胞もインスリンに反応します。軟骨細胞は、マトリックスと呼ばれる、関節軟骨がくっついている部分を作り保持します。
マトリックスは、主にコラーゲンで出来ており、軟骨細胞がそれを作る際に必要とする物質がグルコースです。軟骨細胞はインスリンによりグルコースを取り込むことが必要ですが、インスリン抵抗性の場合は軟骨細胞がマトリックスを保持できなくなり、結果として関節軟骨が弱くなるのです。
もうひとつの関節にとって重要な部品が、関節の潤滑油である関節液(synovial fluid)です。関節液は、滑膜細胞(synoviocytes)という特殊な細胞で出来ています。これは、軟骨細胞同様に、関節がスムーズに動くために非常に重要な働きをしています。この滑膜細胞が、過剰なインスリンに遭遇すると、免疫細胞の侵略を受け炎症を起こし、関節液の生産が減少します。潤滑油が減れば、関節は痛むのです。
骨関節炎は、関節リュウマチ(rheumatiod arthritis)と混同してはいけません。関節リュウマチは、関節の慢性炎症です。炎症を伴うので、関節リウマチはインスリン抵抗性を生じやすいと言えます。この病気の深刻さは、インスリン抵抗性があればひどくなりがちです。
痛風(gout)
痛風は、関節に尿酸結晶が堆積し、炎症が起こる病気です。発生するのは、足(特に親指)や、足首、指、肘などです。
尿酸は、通常は腎臓から尿に分泌されて、体外に排出されます。しかし、インスリン抵抗性の場合は、尿酸は腎臓にため込まれるようになります。血液中で尿酸が溜まり、関節に辿り着き、局所的炎症を引き起こし、赤みや腫れなど痛風によくある炎症反応が起こるのです。
筋肉、骨、皮膚は、同じように体をつなぎ合わせ、一体として動くことを助けています。これらの組織は、インスリンによって強さを保つ必要があります。
8. 胃腸と腎臓
私たちの腸と腎臓は、体をクリーンに保つ重要な役割を負っています。体のシステムに有害物質が侵入し滞在することがないように阻止し、排除するように働きます。どちらもインスリン抵抗性になりやすいです。
インスリン抵抗性のある(2型糖尿病の人の)実に63%が、胃腸の問題を抱えています。また、これが腎臓疾患の主要な原因にもなっています。ですからインスリン感受性は、胃腸や腎臓の健康にはとても重要です。
インスリンと消化
消化管とは、口から肛門までの一連の繋がりのみならず、肝臓、胆嚢、膵臓などの関連臓器もすべて含みます。これらの全てが一体となって食べ物を消化し、栄養素を腸から血管へ流します。
このプロセスには、複数の代表的なステップがあります。まず、食べ物を噛んで飲込み(唾液の中の酵素は消化プロセスを開始します)、食べ物は消化管中を移動し、特定の腺が消化物質を消化管中に分泌し、これらの物質が食べ物を小さな分子に分解し、それらの分子は消化管の細胞を通過して血液中に入ります。
どのステップも、前のステップが正しく作動することが求められます。そして、インスリン抵抗性は、これらの全てに対して問題を起こすのです。
逆流性食道炎(Reflux Esophagitis)
食べ物を消化するのに、胃は極めて高い酸を生成します。胃が酸に対して大丈夫なのは、濃厚な保護粘液を出すからですが、食道炎は酸に耐えられず、食道下部括約筋という環状の筋肉は、胃から食道を閉鎖してしまいます。
しかし、時々胃の内容物が食道に逆流します。食道は濃い胃酸に対する防御がないので、食道下部に潰瘍ができるのです。
40%近くのアメリカ人成人は、逆流の症状である胸やけを経験しています。アメリカ人成人の約半数がインスリン抵抗性であることを思い出せば、メタボリック症候群は逆流性食道炎と非常に関連性が強く、また慢性疾患の胃食道逆流症とも関連するのです。
特に、メタボリックシンドロームの2つの症状がここで繋がります。すなわち、腹部肥満とインスリン抵抗性です。腹部肥満との関連性は簡単に説明できます。体内の中心部に脂肪が溜まると、胃を含んだ近くの組織を圧迫します。その結果胃が受ける圧力が増し、食道下部に逆流が起こるのです。
前にも触れたように、インスリン抵抗性は、腹部肥満を引き起こします。しかし、腹部肥満が、逆流の明らかな犯人であったとしても、自分からそうなる訳ではないのです。
様々な生活習慣の要素を検討した台湾の臨床医は、内臓肥満や高血圧などに関わらず、インスリン抵抗性が逆流症のリスクを15%高め、インスリン抵抗性が悪くなれば、逆流も悪くなることを発見しました。
時間を経て、食道下部は胃酸逆流から自らを守るために、外側の細胞壁をより強固なまるで消化管のようなものに変化させます。この状態をバレット(Barrett’s)食道と言い、インスリン抵抗性と併発しやすいものです。
バレット食道は、それほど危険ではありませんが、飲込むときの痛みを起こします。しかし、細胞が変異を起こし始め、継続的に致死性のものになる可能性はあります。ですから、バレット食道の問題は、食道癌を起こすかもしれないことです。
胃腸炎(gastroparesis)
食べ物を消化管内で移動させる消化管の収縮と弛緩の繰り返しを、蠕動といいます。胃腸炎とは、消化器官、特に胃でのひどい合併症で、麻痺が起こり食べ物を送ることが出来なくなります。結果として食べ物が滞留し、時には胃石と呼ばれる固形物になり、痛みを伴いながら消化管を移動して、細い通路を塞ぐことになるのです。
糖尿病は、胃腸炎の主要な原因です。糖尿病の人は、神経損傷というように特定の神経が損傷するところから始まります。この場合、胃を動かす神経である迷走神経(vagus nerve)が損傷し、胃の収縮と蠕動が上手くいかなくなります。
この神経損傷は、糖尿病で顕著な、過剰な血液グルコースの結果起こると考えられていますが、インスリンだけでも問題は起こります。ある研究で、インスリンを投与して疑似インスリン抵抗性状態を作ると、インスリン抵抗性と同じように、食物の消化管内移動が40%も遅くなることが分かりました。
インスリンと肝臓
臓器の中で担当する生理学的プロセス数を競えば、肝臓がナンバー1になるでしょう。肝臓は血液から毒性物質を除去し、古い血液細胞を廃棄し、ビタミンを保存し、栄養代謝(脂肪、タンパク質、炭水化物などを扱い)などを担います。これほど沢山の重要なプロセスを担うことから、肝臓は注目を集める臓器であると言えます。
肝臓がインスリン抵抗性でない人は、全身的なインスリン抵抗性にはなりにくく、肝臓はインスリン抵抗性になりやすい一番の臓器です。健康な肝臓が血液中のインスリンを感受すると、グルコースを取込み、直ぐに使うわけではなく、体の予備エネルギーとして保管します。そしていくつかのグルコース分子からなるグリコーゲンという物質、または脂肪に変化します。
これにより、血中のグルコース量は減り、インスリン量を減らすことにつながります。しかし、一旦インスリン抵抗性になると、肝臓は特殊な生理学的状況を作り出し、血中のグルコースと脂肪を増やし、LDLコレステロールの大きさを変える可能性を高めるのです。
ふつうグリコーゲンは肝臓や筋肉中に予備のエネルギーを蓄えます。体が、血中グルコースの低下やストレスや消化を助けるために、エネルギーを必要と感じると、グリコーゲンはグルコースに戻り血中に放出されます。
インスリン抵抗性だと、インスリンは肝臓に取り込んでグルコースをグリコーゲンにせよという指示をしません。このシグナルが無いので、グルコースとインスリンの血中濃度が高くても、肝臓はグリコーゲンを壊してグルコースを血中に放出しますので、更にグルコース濃度もインスリン濃度も上がってしまうのです。
脂肪に関しては、また別の問題が発生します。健康な肝臓の場合は、インスリンは肝臓に余剰グルコースを取込んで、脂肪に変えるようにします。この脂肪の一部は肝臓に、一部は血中に保管されます。典型的な高インスリン血症はインスリン抵抗性を併発しますが、上記の現象がより普通に発生します。
言い換えると、過剰なインスリンのシグナルが、肝臓に対して過剰な脂肪を作るように言うのです。この流れでは、2つの危険な問題、すなわち脂質異常症(hyperlipidemia)と脂肪肝を引き起こします。
脂質異常症
前に、インスリン抵抗性が、脂質異常症(dyslipidemia)を引き起こすことを説明しましたが、インスリンは血中のコレステロールを好ましくない方向に変化させます。一方、高脂血症(Hyperlipidemia)は、血液に脂肪が過剰で、リポ脂質(LDLコレステロールと、その前駆体のVLDLコレステロール)も発生している状態です。
肝臓が、脂肪を生成する場合には、よく成熟した脂肪であるパルミチン酸を作ります。これは正常ではなく、血中の成熟脂肪は、炎症性が高く、循環器系の合併症を起こしたり、インスリン抵抗性を悪化させたりします。そして重要なのは、これは脂肪を一切食べなくても起こるという問題です。
非アルコール性脂肪肝
肝臓は、脂肪を血中に流すよりも、蓄えます。もし肝臓が過剰に脂肪を蓄えた場合には、機能を失い始め、より深刻な合併症を発症します。肝臓の場合、過剰な脂肪とは、その重さの5%から10%を指します。
歴史的には、アルコールの飲み過ぎによる脂肪肝が有名です。他の組織はアルコールを代謝できないので、アルコールの飲み過ぎは時間の経過と共に細胞内に脂肪を蓄積し、アルコール性脂肪肝となります。しかしながら、飲酒しなくても脂肪肝になることがあります。
この数十年間の間に、アメリカ人のおよそ3人に1人が非アルコール性脂肪肝(NAFLD)なのです。この病気は30年前にはまだ誰も聞いたこともなかったのですが、今では西欧諸国で最も耳にする肝疾患です。これが、インスリン抵抗性と非常に関連が深いのです。
インスリン抵抗性が、インスリン感受性の高い人とくらべて、15倍もNAFLDになる可能性が高いということで、インスリン抵抗性がNAFLD予測の一番の指標となっています。肥満の人はほとんどNAFLDですが、痩せている人も、インスリン抵抗性であれば、NAFLDになる可能性は極めて高いと言えるのです。
脂肪肝は、以前は良性なものと考えられてきましたが、最近の研究では逆の結果が出ています。NAFLDは、死につながる深刻な肝疾患に発展する可能性があり、インスリン抵抗性がそれを加速してるのです。
もしNAFLDを発症すれば、肝臓は炎症化し、肝線維症という肝臓障害に発展するのです。NAFLD患者のほぼ半数が、繊維化を起こします。その後NAFLD患者の5分の1が肝硬変(cirrhosis)を発症し、生存のためには肝移植しかないという状態に陥るのです。また一部の人は肝疾患ではなく、肝臓癌を発症するのです。
インスリンと胆嚢
胆嚢は、肝臓の右下に位置し、肝臓と共に食べた脂肪を消化しています。胆嚢には、肝臓で作られる胆汁という液体を貯蔵する役割があります。胆汁は、ほとんど水と、塩、ビリルビン(古い赤血球からなる物質)と脂肪から出来ています。
これらの物質は一緒に働いて、消化器内で脂肪を乳状に変え、体内に吸収されやすくします。胆汁の保管倉として働くことにより、胆汁は脂肪を消化しやすくしているのです。
胆嚢の不具合は、胆汁の濃度が高くなり過ぎて石化する場合が最も多いです。
胆石(gallstones)
胆汁は、2方法により胆石を作ります。肝臓が過剰なコレステロールを生産する場合と、、胆嚢が消化器内に胆汁を十分に提供できない場合です。インスリン抵抗性は、このどちらも助長します。
過剰なコレステロールの場合、胆石は、胆汁にビリルビンかコレステロールが多すぎる場合に作られます。肝臓は、古い赤血球を体から廃棄する役割を持っており、ビリルビンはこの古い赤血球の一部なのですが、インスリン抵抗性はこの部分には関係がありません。
しかし、肝臓のコレステロール生産には非常に関連していますs。コレステロールは血中に出されるか、胆汁に入り込んで胆嚢に保存されるかです。ですから、体がインスリン抵抗性になりインスリン値が高くなると、肝臓は普通より多くのコレステロールを生産することになり、過剰のコレステロールで胆汁を濃くしてしまうのです。
インスリン抵抗性が、世界中で一般的なほとんどはコレステロール石の胆石の原因であることは、いくつもの研究で明らかになっています。
肝臓は、栄養プロセスの制御に欠かせない臓器です。しかし、毒性物質の廃棄という点においては、単独では働けず、腎臓がフィルター機能を果たしています。
腎臓
腎臓は、肝臓と共に毒物を体内から排除し、尿に排出します。フィルターとしてだけでなく、腎臓は多くのプロセスに関与しています。血液量の制御、骨の健康、pHバランスなどです。
腎石
腎臓は、最も痛みが強いと言われている腎石を発症します。腎石は、まず、尿結石として知られるように、腎臓で作られます。この際にインスリン抵抗性が役割を果たしていて、腎石を作るのに最適な環境を提供しているのです。
まず、血中の高インスリンは、血中カルシウム量を増やします。カルシウム過剰は、心臓を傷めたり、最もふつうの腎石を作ったりするのです。血中高カルシウムは病気を引き起こしがちで、腎臓はこの過剰カルシウムをフィルターしては尿に少しずつ出します。
血中カルシウムが高まれば、腎臓は通常より多くのカルシウムをろ過します。そしてある時、尿がカルシウムで過飽和状態となります。この時点で、カルシウムは結晶化し、石化するのです。
過剰なインスリンが過剰なカルシウムを引き起こす方法が興味深いです。インスリンは副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone、このホルモンはインスリン抵抗性を起こすのですが)量を増やします。このホルモンの主要な役割は、消化器官の中の食べ物から吸収するカルシウム量と、骨から再吸収するカルシウム量を増やすことで血中カルシウムを増やすことです。
インスリン抵抗性と腎石をつなぐ2つ目の関連性は、尿の酸化とアルカリ化、又はpHを測ることに対する働きです。腎臓が、正常な体内のpHを保つことに関係していることから、尿は体のどこよりもより酸性に出来ています。インスリン抵抗性により、腎臓が尿に排出する酸を作れなくなると、尿がアルカリ化して、多くの分子が分解されにくくなり、結果として結石が生まれやすくなるのです。
腎臓疾患
腎臓疾患は、ろ過機能を失うことですので、致命的です。2型糖尿病が主たる原因ですが、2型糖尿病はインスリン抵抗性です。ですからインスリン抵抗性は腎疾患リスクを50%も高めるのです。
インスリン抵抗性の人はインスリン感受性の高い人に比べて4倍も腎臓疾患のリスクが高いのです。そして、これはグルコース値が正常であっても起こるというところが肝心です。
インスリン抵抗性が、実際にどのように腎疾患を導くのかは分かっていません。インスリンは、腎臓のろ過装置を肥大化させ、分子が血液から尿に排出されるのがより困難になるのではないかと考えられています。
肝臓疾患の人の死亡率は、肝疾患の無い人の3倍以上になっています。ですから、リスク要因であるインスリン抵抗性などは、なるべく早期に察知すべきです。もし従来の指標にばかり頼っていたら(2型糖尿病の診断基準である高グルコース値など)、手遅れなのです。
インスリン抵抗性を示すような高インスリン値は、グルコースが高くなる何年も前から高くなっているのですから、これを測定すべきなのです。
9. メタボリックシンドロームと肥満
メタボリックシンドロームとは、アメリカの成人の3人に1人は該当し、およそ90%以上は何らかの兆候をひとつは持っていると言われています。WHOはメタボリックシンドロームを2つの要員で定義しています。
ひとつは、患者が、高血圧、脂質異常、内臓脂肪型肥満、尿中タンパク質低下の4つの内の2つを持っていること、ふたつ目は、患者がインスリン抵抗性であることです。
つまり、インスリン抵抗性と2つの問題を合わせ持てばメタボリックシンドロームなのです。
肥満は誰もが忌み嫌うものです。肥満とは、体に過剰な脂肪がある状態ということで、インスリン抵抗性や高インスリン症がもたらした代謝の結果であり、インスリンが他の要素と相まって細胞の成長を促し、脂肪が使われるのを妨げたのです。しかし、肥満とインスリン抵抗性の関連性は単純ではないのです。
肥満とインスリン抵抗性:その複雑性
肥満とインスリン抵抗性の関係は、卵とニワトリの関係のようにどちらが先だったかという話に繋がります。
肥満とインスリン抵抗性は、同時に起こる傾向にあります。過剰な脂肪はインスリン抵抗性と関連が高いことは明らかです。体重過剰な肥満の人の70%がインスリン抵抗性です。
しかし、その関係性が研究され始めた30年前から、現在に至るまで、肥満がインスリン抵抗性を起こすのだという結論が大半を占めてきました。ですから体重を減らせば、インスリン抵抗性は改善するという話です。
なぜ脂肪がつくのか
肥満研究は、まずそれがホルモン異常であるという理解からスタートしました。しかし、1900年代半ばに、摂取カロリーの差によるという説に取って変わられました。
しかし、実際には体はそれほど単純には説明できません。多くのホルモンが、エネルギーをどう使うか蓄えるかを決めていますが、その部分が欠落した議論となっているのです。
そして、脂肪について一番作用するのがインスリンということになります。つまり、インスリンが多ければ脂肪は増え、インスリンが少なければ脂肪は減るのです。
10. 弊社からのコメント
弊社がなぜインスリン抵抗性のマネジメントが重要だと考えるかといいますと、生活習慣病(老化性慢性疾患)を予防することこそが、ロンジェビティ医療の根幹であると思っているからです。今後も、このような情報発信を続けていきたいと思います。